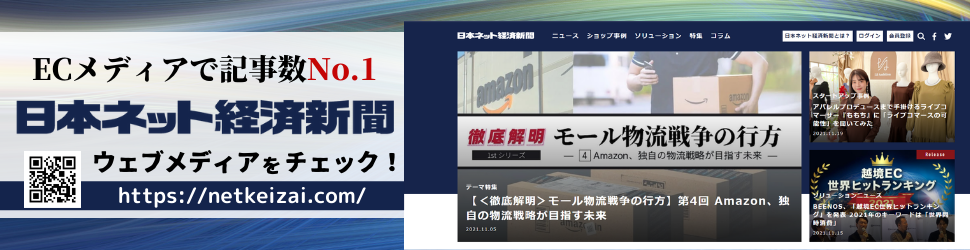2022年 有力EC事業者・有識者が市場を予測
- 2022/01/13
- 日本ネット経済新聞
- 2022年 有力EC事業者・有識者が市場を予測
有識者に聞く!【2022年 EC市場展望】〈OMO〉

さくら
ECコンサルタントとして活躍している合同会社さくらの仲庭拓也代表は、EC企業10社以上でEC事業の責任者を務めている。大手小売企業や有名ブランドも支援しており、OMO(ネットとリアルの融合)の推進もサポートしている。仲庭氏は、「オンラインとオフライン両方を利用している顧客は、片方を利用している顧客よりもLTVで4倍以上の差が出る事例もある」と話す。仲庭氏にOMO戦略で必要なポイントを聞いた。
OMOの一環として、BI(ビジネスインテリジェンス)やMA(マーケティング・オートメーション)ツールの導入が加速度的に進んでいる。オンラインとオフラインの購買・顧客情報をBIツールによりRFM分析、それらの情報をもとにMAツールでメール、LINE、SMSなどで個々の顧客に情報を配信する仕組みを導入する企業が増えている。
送付内容はAIで自動的に購買データから制作し、送付先についても、購入しやすい客層をAIが自動的に判断してセグメントを作成するシステムもできている。
ただ、現実は二つのOMO導入障壁がある。一つには、コロナ禍において、オフラインで購入しにくいため、オンラインの利用者が増えたように、オンラインの利用者を増やすためには、利用する必然性が必要になる。
そのために、企業側の努力として、ターゲット層に最適化された接点をできる限り作り出すことが求められる。オンラインを利用する利点(オンライン限定商品・販促など)を作り、一度でもオンラインで購入することが良い体験であることを認識していただくことが必要である。
二つ目の障壁は、実店舗からECへの送客の難しさだ。その理由は、(1)実店舗の売り上げが高く、ECは一つの店舗としか位置付けられていない(2)実店舗スタッフのEC送客に対する抵抗感(3)実店舗のPOSシステムとECシステムの連携が困難─などがある。
OMO推進のためには、重要性を認識したメンバーが社内を説得して、会社の方針として特にオンラインの重要性を唱える必要がある。
OMOを潤滑に進めるために(1)顧客に多方面でつながり、タッチしていく仕組み(複数接点)(2)顧客が望んだときに望んだ情報や商品を必要な分だけ提供できる仕組み(顧客に親切な仕組み)(3)オンラインを使いたくなる仕組み(オンラインを利用する必然性)(4)社内共通認識(「OMO会社方針」を作る)─の四つの戦略が必要となる。
- 2022年 有力EC事業者・有識者が市場を予測
- List
事業者に聞く!【2022年 事業戦略】

バルクオム

アサヒグループ食品

cotta

ワークマン

ユナイテッドアローズ

高島屋

ルームクリップ

タンスのゲン

ストリーム
有識者に聞く!【2022年 EC市場展望】〈資材調達難〉

shizai

いろは
有識者に聞く!【2022年 EC市場展望】〈越境EC〉

フューチャー
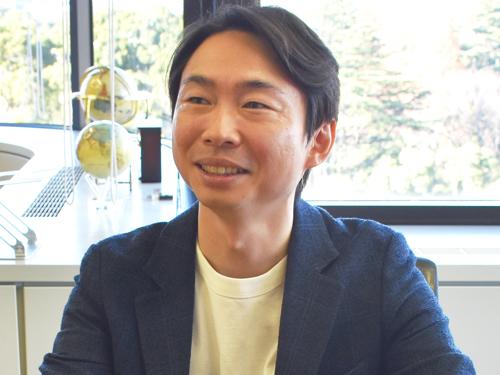
BEENOS

キレイコム

ワサビ
有識者に聞く!【2022年 EC市場展望】〈メタバース〉

〈メタバース〉一般社団法人 ジャパンEコマースコンサルタント協会

HIKKY
有識者に聞く!【2022年 EC市場展望】〈動画コマース〉

サムライパートナーズ
有識者に聞く!【2022年 EC市場展望】〈コンプライアン〉