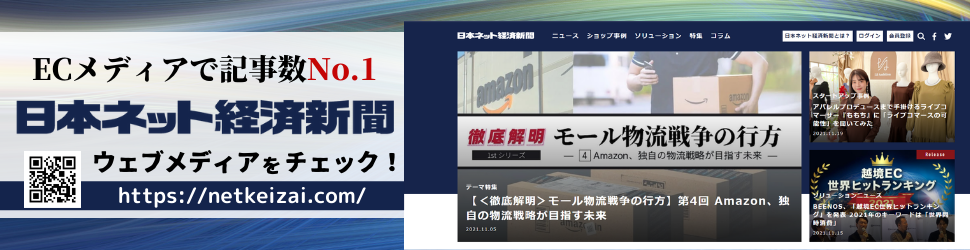「ペットの健康」に着目して開発された、ペットフードやペット用サプリのECが、近年急増している。そういった商品の広告表示には、「〇〇が治る」「〇〇に効果がある」といった、薬機法違反の表現も散見される。コンプライアンスに課題を抱える事業者が少なくないようだ。ペット関連の法規制に詳しい弁護士によると、法令違反の表示が増える背景には、「事業者の法律に関するリテラシーが低い」「チェック体制が整っていない」「小規模事業者が多数存在し、管理が行き届きにくい」といったことがあると考えられるという。事業者の法令順守を後押しすべく、ペットフード公正取引協議会(所在地東京都)や日本ペット用品工業会(事務局東京都)などが、広告表現についてのセミナーを開催したり、サイト上で解説などを行ったりしているものの、加入している企業はまだまだ少ないのが現状だという。
■能動的な確認が少ない
ペットの家族化?が浸透するにつれ、ペットの健康を気遣う飼い主が増えている。こうした背景から、「ペットの健康」に着目した製品が増えている。
健康志向のペット用食品などで違法な広告表示が増える背景について、ペットフード公正取引協議会の山本敦事務局長は、「ペットフードの表示は、農水省が所管する中でも、比較的新しい分野だ。そのため農水省が(違反表示について)能動的に確認するケースはまだまだ少ない」と話す。
現在だと、同団体が買い上げ調査などを行い、定期的に農水省への報告を実施し、その後農水省から指導があるケースがほとんどだという。「指導があったタイミングで表示を変更すれば問題ないケースが多いことに加え、そもそも指導の機会が少ない。指導が入るまでは、問題のある表示のままでいいと考える悪質な事業者もいるのが現実だ」(山本氏)と話す。
現在、ペットフード公正取引協議会には、ペット関連の事業者が約80社、日本ペット用品工業会には約120社が加入している。国内のペット関連事業者の数が、個人事業主を含めると、数万単位でいることを考えると、加入者数がまだまだ少ないのが現状となっている。
ペット法務に精通するなかま法律事務所の代表弁護士を務める中間隼人氏も、チェック体制が整っていないことを問題視している。「人向けの商品の広告に比べ、まだまだ体制が整っていない。実際に行政処分を受けた事業者もわずかだ」(同)と話す。
中間氏は、「ペットフードやサプリは、『雑貨』として区分される。そのため『規制があると知らなかった』という事業者も少なくない」と話す。
■「顧客の声」にも注意
ECサイトや広告で頻繁に目にする「顧客の声」にも注意が必要だという。
中間氏によると、「顧客の声だからと、もらった内容をそのまま載せているケースが少なくない。『このサプリをあげたら、涙焼けが改善した』『口臭がなくなった』といった声を掲載している場合がある。多くの企業が『顧客の声』を掲載しているだけに、注意が必要だろう」としていた。「表現的には、健康維持やサポートといったように、現状維持の表現にとどめるのが良い」とも話す。「SNSの投稿は、頻度が高く気軽に文言を書いてしまいがちだ。だが適用されるルールは、広告やLPと一緒だ。社内での、SNSのチェック体制が甘いケースもあるため、より注意が必要だ」(同)とも話していた。
■疑問視される「獣医師監修」
ペットECのLPや広告に使われる、「獣医師監修」といった表現にも、業界からは疑問の声が挙がっている。
(続きは、「日本流通産業新聞 4月3日号で)
【ペットEC市場】コンプライアンスに課題/悪質な「獣医師監修」商品も(2025年4月3日号)
記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。